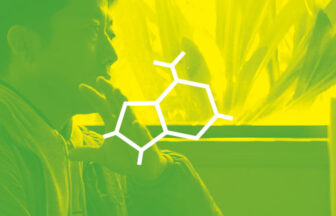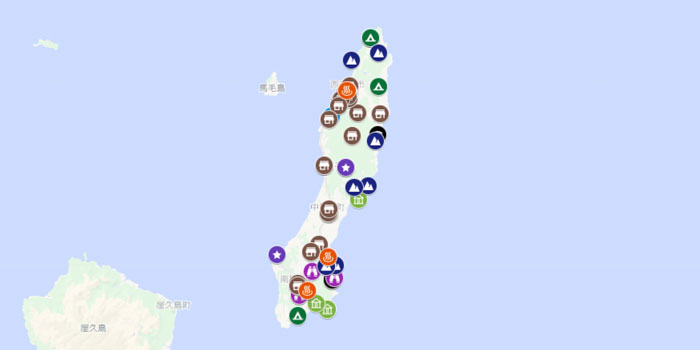|古市農園・有限会社新栄物産|古市純一さん 幸代さん夫妻

種子島は超早場米コシヒカリの産地だと耳にして、「えっ!?」と思う島外の人は多いはずだ。それどころか、平地が限られている離島で広大な水田を必要とする米作が盛んだと言われてその田園風景が想像できるだろうか。
はじめて種子島を訪れて、宇宙センターに向かう途上南種子茎永あたりの田園風景を目の当たりにした旅行者は、そこで作られているのがコシヒカリだと聞いて、一様に驚きの声を上げる。ここは間違いなく米どころ。40年にわたって種子島で米作りに向き合ってきた古市純一さんご夫妻の話を聞いた。
それはみかんの失敗からはじまった
南種子町で古市農園を経営する古市純一さん(65歳)は、稲作、コシヒカリの栽培をはじめて40年になるベテランだ。30haの作付面積は島で最大級だが、それは今もひろがり続けているそうだ。
しかしその歩みは順風満帆でも順調でもなかった。純一さんは振り返る。
「紆余曲折、試行錯誤、言ってみれば苦労の連続ですよ。家内にも苦労かけました」
そう言って彼は優しい視線を妻幸代さんに向けた。
高校を卒業すると純一さんは本土で果樹栽培を学んだ。南西の島嶼(とうしょ)、特に種子島、屋久島、奄美大島のタンカンは甘くて美味しいとされていた。彼はその栽培を学んで帰島したのだ。それは母方の叔父が経営する果樹園で働くという目的があったからだ。
しかし、
「3年ぐらい過ぎた頃でしょうか、果樹園の資金繰りが悪くなったのは。次々と従業員が辞めてしまいました。悶々とした日を送っていいましたね。親父は農協か役場の果樹の技術員として務めろと言いましたが、僕はそんなつもりで帰ってきたのではないと、親父と大喧嘩になりました」
そして純一さんの心に火がついた。だったら自分がやってみせると。
純一さんは2,600万円の借り入れを起こし6haの果樹園を引き継いだ。25歳の時だった。今振り返ると無謀な決断だったと思う。その直後に台風による塩害に見舞われた。
「結婚した年やった。台風で潮が上がって……。みかんも大きくなってついた実が全部落ちて、木も枯れた」
当時を思い出した純一さんの表情は暗かった。幸代さんが言葉をつないだ。「その直後に結婚したんです。農地からはじめて、ゼロからのスタートだったのですが。ゼロどころかマイネスからのスタートになりました。結婚生活も暗いスタートでしたよ」
40年経っても昨日のことのように思い浮かぶに違いない。
だが純一さんの決断は早かった。
「みかんにこだわって、また一から木を育てるのは、生活するにも大変ややろうなと。だったら米を作ろうと思いました。みかん畑を1年かけて6ha全部を自分で田んぼにしたんですわ」
当時南種子ではコシヒカリの生産に力を入れはじめた頃だった。1俵30kあたりの出荷価格が12000円と高かったという。だから米作農家はコシヒカリをできるだけ早く出そうと努力したと。
「産地自体が大きいわけでも、出荷量が多いわけでもないので、日本一早く出荷しないと価格競争で取り残されていく。だからみんな必死になって作りました」
「それにしても」と幸代さんは言う。「6ha購入した資金の借り入れを毎年少しずつ返済して、その上に生活を成り立たせないと……。そら豆とかお金になるあらゆる作物を作り返済してきました。もちろん農業だけではとても無理だったので、主人は土建業にアルバイトで勤めていました。並行して牛を2、3頭から飼いはじめてね。そうやってだんだん生活を軌道に乗せて試行錯誤しながら、米作と畜産に集中できるようになってきたんですよ」
その矢先だった。純一さんが仕事中に右足の膝の大怪我をした。鹿児島本土の病院で手術、その後1年はリハビリで仕事が出来なかった。それでも何とかここまでやってこられた。
40年は言葉にすると簡単だ。だが、幸代さんが話す側で純一さんが「夜も寝ないでね」とつぶやいた時、彼女は大きくうなずいた。
塩害によるみかんの失敗。すべてはそこからはじまったのだ。

1年を頑張り、40年を重ねて
40年という時間の蓄積は大きい。古市農園はこの間に水田30haを耕作し、牛40頭を飼育する規模になった。これは経営規模が大きくなり、働く人が増えたということではない。
「5年ぐらい前までは、ほとんど2人でやってきました。耕作する面積が増えてもずっと2人」
そう言って笑った純一さんに一番の苦労は何かとたずねた。
答えてくれたのは幸代さんだった。
「除草、草引きですよ。種子島は暑いので、手を抜くとすぐに草が生える。あまり使いたくはないけれど、最低限の除草剤は使います。でも、食べていただく方の安全安心のことを思うと、やはり手で草を抜くのがいいですよ。田んぼの中を這うようにして草を取るので、その作業が大変。正直に言うと嫌になりますね。自分との闘いと言ってもいいかもしれないです。それ以外はずいぶん機械化されてきたので楽になりましたけど」
純一さんが続けた。
「機械を動かすのは男の仕事。草引きは女の仕事。やから家内が大変かも」
働き手を雇用することは考えなかったのだろうか。
「1月から6月までが田植えの準備と田植えの時期、7月から8月までが収穫の時期、その期間は猛烈に忙しい。8月なんかはセンターに泊まり込んで籾すりして、朝4時にシャワー浴びて5時には夜が明けるから収穫に出て……。その時期だけ雇用を確保しても後の期間が暇になってしまう。年間通して雇用するのがいいのだけど、そこがなかなか難しい。9月から12月は秋の耕転と田んぼの土手の草払いだけなので、ちょっと楽になる。1年を通じたメリハリだね」(純一さん)
頑張れば人を雇うほどでもない、のだ。それで現在の30haに拡大するまで、夫婦2人で頑張ってきたのだ。いや、2人だから頑張ってこられたと言ってもいいかもしれない。
10月、11月のたった2カ月の農閑期。実情を知らない人からは全部収穫した後だから暇だろうと言われるそうだ。だが、純一さんは、農閑期の過ごし方が一番重要だと言った。その時にどのように働くかによって、次の年の全てが決まると。
「来年に向けて草払いをしたり、畝をあげたり。水をちゃんと切らんと土が生きてこない。1反分の収量が1俵落ちると、うちの総作付面積に換算すると120〜130万円の減収につながる。それ考えると、この時期にできることはすべてやらなければならないんですよ」
息を抜くところがない。ひたすら米に向き合い、土と向き合う日々が続くのだ。
「人間息抜きがないと健康にも悪いでしょ」幸代さんは笑った。「ストレスもたまるし、病気にもなりそう。だから少々忙しくても時間を見つけて孫のお遊戯会に行ったり、バレーボールの試合の応援に行ったり、主人は大好きな釣りに出かけたり。そんなことで気分転換をして、暮らしを楽しみながら労働に汗を流す。そういう臨機応変なところは農家のいいところでしょうね。自由に時間を使えるところがね」
そう言えばこの取材も、「孫の保育園のおゆうぎ会」(幸代さん)の帰りに応じてくれたのだった。「やるべきことはちゃんとやっているから、そういう楽しみのための時間もやりくりできる」のだと。
2人はそうやって1年を頑張り、40年を重ねてきたのだ。


美味しいというひと言で
苦労はまだある。
消費者の立場から言うと安全・安心は普通に担保されて当たり前なのだ。そこにどれほどの生産者の苦労があろうと当然のことなのだ。
純一さんの父親は、平成2年に現在彼自身が引き継いでいる有限会社新栄物産という会社で籾すりと出荷をメインに事業を立ち上げた。農家からコメを集めて籾すりして鹿児島の集荷組合に玄米を卸すという事業だ。
古市農園は鹿児島本土にある集荷組合を通じて全国に販路をひろげている。
「そこが東京の生活協同組合を紹介してくれて、バイヤーが毎年6月くらいに来て田んぼや稲のなどの状況を査察するんです。そこで一定の基準を満たさないと出荷できない。1度でも不具合があればそれでダメになる。消費者の安全安心もあるけれど、自分としても自信を持っていいものを出さないと取引は続かないですよ」
純一さんによると東京の生協には毎年玄米で6000kほどを出荷しているそうだ。特に放射性物質やカドミウムの含有量に厳しい基準が設けられているという。
「収穫する1週間前に籾を送ってカドミウムなどが含まれていないか検査をする。種子島でもうちのところだけです。特に生協はなかなか厳しい。農薬もですね。畜産でも、牛の飼料、草とかはどこのものを入れてるか。自分が作った米、育てた牛を一定の、しかも厳しい基準に照らして評価されるわけです。自分自身を厳しい目でチェック、管理しないと信頼は獲得できないということです」
その結果として、どこに出しても自信を持って安全・安心を自負できるのだ。しかしそれは、すごく手間暇がかかり苦労しなければならないところでもある。
「水の管理はもちろんだけど、堆肥も生のままよりも完熟して、さらに家内が一生懸命切り返して1年寝かしたのを田んぼに入れたり……。手を抜かないということですよ」(純一さん)
「農産物は血と汗の涙の結晶。手間暇かけてつくってはじめて、買っていただいたみなさんに安心して口に運んでもらって、美味しいと満足してもらってはじめて報われる。そこが私たちの一番の喜び。満足の中にはもちろん安全で安心ということも含まれるんです」(幸代さん)
一つひとつの苦労が噛み合って結実して安全安心、そして満足につながっていく。無駄な苦労は何もないのだ。どんなに苦しくても、美味しいというひと言ですべてが解決できる。そのために農家は生産者としての惜しみない努力を積み重ねるのだ。
「苦労と努力が伝わるかどうかは難しいところだ。苦労が実っていけばいいなと願いながら毎日の作業を続けています」
純一さんは表情を引き締めた。
種子島の米作りを担う

30haの耕作面積といえば、恐らく種子島では一番の規模になるだろう。しかしそれはまだまだ拡がり続けていくということだ。なぜかと言えば、高齢化が進んで農作業ができなくなり離農せざるを得ない農家が増えているからだ。離農する農家の立場に立てば、代々受け継いできた農地が荒れていくのを見たくないのは当たり前だ。同じ地域で頑張ってきた農家にとっても、身近な農地、親しんできた田園風景が荒廃していくのを見るのは辛いことだ。
「そういう農家も、そういう農地も確実に増えています」純一さんが言った。「でも、その中で受け継ぐ農家がなかなかなくてね。その面積を受け入れられる農家もそんなにないし、結局は私たちみたいに手広くやっているところに依頼が来て……。そうなると受け入れなければと思ってしまいますよ」
「手広くやっている」と言っても、トラクター、田植え機、さらには乾燥機などの設備と、それなりの機械化と設備の近代化を進めてきた結果で、働き手としては夫婦2人が主になっている。
「もともと農業が好きだという思いでやってきましてけど、好きなだけではねえ……」
幸代さんはじっと純一さんを見た。
「好きな上に、農地を守っていくために受け入れようという使命感ですよ。僕にとっては種子島の農業を守る、農地を守るというのが究極のエコロジーなんです。この環境を守らないと、どんなに苦労しても、どんなに汗を流しても、いい作物はできませんからね。でもそれが私たちも高齢になって、どんどん規模を大きくしていって、果たしてどこまでできるのだろうかという不安もなくはないです。葛藤ですよ」
「自然の流れとして増えていく。でもからだはひとつなので、いくら機械を大型化しても操作するのは1人なんです。後継者が5年くらい前にできたんですけど、でも、まだ将来的に面積が増えてくると、とてもじゃないけどお父さんと2人じゃできないです。その時の対策をどうするか。働き手、機械のオペレーターの確保ですね。お父さんはどんどん歳をとっていく一方ですからね(笑) 若い力がどうしても必要になるんです」
「実は……」と純一さんが頭を掻きながら言った。「母ちゃんに黙っとったけど、今年も約2haほど増えたんやわ。増えたって言ったら叱られるから。またかって(笑)」
夫婦は、自分たちの農業はもちろんだが、種子島の農業、種子島の米作りを守り抜く決意をしているように思えた。
大地に描き続ける人生
5年前にきた後継者とは?
「三女の婿ですよ。うちは娘ばかり3人で、長女は西之表市の他家に嫁ぎ、次女は島外で就職していました。三女は京都で仕事をしていたのですが結婚を機に島に戻り、その婿さんが農業に就いてくれたんですよ」
夫婦2人ともうれしそうに笑った。後継者となった彼はもともと滋賀県出身で実家は非農家、彼自身はサラリーマンだった。もちろん農業経験が全くなかった。「三女と結婚するまでの間に種子島に遊びに来て、島が好きになったそうだ。
「農業にも興味を持ってくれたみたいで、結婚を契機に勤めを辞めて就農してくれた。その決断が良かったのかどうかはまだまだこれからのこと。今は必死になって毎日働いている」(純一さん)
「本人も勇気がいったと思うけど、ご両親もよく認めてくれたと思う。大変だっただろうな」(幸代さん)
彼が後継者になってくれて5年。純一さんは畜産の部門をすべて任せた。
「あとは婿が色んなところで勉強した知識とか技術でうまくやってくれる。新しいこともどんどん取り入れている。若い世代が集まった勉強会や研究会にも参加しているので、そこはどんどんやってもらって新しい取り組みとかも進めてくれたら良い。削蹄師の免許も取った」
純一さんは、やり方も方針も違うのですべて任せて、一切口は出さないのだと言った。
「しかし」と幸代さんが続けた。「牛が病気にかからないかなどは、ちゃんと見守っています。子牛というのはデリケートで、生後1カ月までは病気で死ぬことも少なくない。そこは経験があるからこそわかることもあるので。あとは発情とか。環境の管理には気を使う。そういうチェックには私たちが気を使い見守っています」
農業というのは難しい。季節、気候を読んで、さらに生き物を相手にして、どのように動いていくか。経験に基づいた知識が必要になる。農家で育ったなら、1年を通してどんな作業をするのかなんとなくわかるような気がするが、非農家出身者にとっては難しいはずだと夫婦は気遣った。
さらに次女も島に戻り、長女も相次いで経営に加わった。純一さんが父親から受け継いだ新栄物産は、もともと籾すりと集荷がメインだったとは先に述べた。そこに娘たちや新しい家族が加わり食品加工部門、直販部門、ネットショップを立ち上げた。
「子どもたち3人が集まって和気あいあい作業を進める風景はなかなかうれしいものがある」
純一さんは目を細めた。今注目を集めている赤米を使った商品は彼女たちの発想負うところが大きい。加工の話は前からあったのだけど、夫婦2人では手が回らなかった。赤米も最初は玄米で売っていたのだが、玄米では販路も拡がらない。で、子どもたちが帰ってきたことをきっかけに加工場を立ち上げて、色んな商品企画も進めている。それは、2018年に開催された熊毛地域特産品コンクール食品部門で「赤米甘酒アイス」が最優秀賞に選ばれるなどすでに成果として現れている。
「娘たちのアイデアは大きい」と幸代さん。
「私たち夫婦がものづくりと経営の基盤を作って、その上で子どもたちの世代で新しいことをはじめていく。実際販路も拡がりました。ネットを駆使してHPを立ち上げて、ネットショップをオープンして、白米にせよ赤米にせよ、どんどん全国に向けて発信している。とても心強いですね」と純一さん。
商品企画、パッケージのデザイン、すべてにわたって娘さんたちの力が発揮されている。
「楽しいことはいっぱいあるけれど、お互いが真剣だから、親子とは言え衝突することもしょっちゅうある」
後継者難が継承をものづくりの段階で止めてしまう例を数多見てきた。経営を継承するという段階にまで高められないのだ。しかし、ここ古市農園と新栄物産では、農業という伝統のものづくりはもちろん、時代に適応しようとする経営のあり方が受け継がれている。
純一さんと幸代さんの40年は、南種子の大地に人生を描いてきた歴史だった。それこそが生きていくための哲学だと教えられたような気がする。そしてそれはこれからも果てしなく続いていく。もちろん苦労は続くだろうが、農家として、家族として、どのように発展・進化していくのか興味が募る。